前回の【necoの育児】妊娠高血圧腎症で管理入院|誘発分娩の流れと出産レポから、
だいぶ間が空いてしまいました。
私はというと、10月末のマラソン大会に向けてランを、
小学生組は運動会の練習に、そして週末は野球の試合と、
親子そろってシーズン真っ只中のバタバタな日々を過ごしていました。
そんなわけで、少し“今さら感”もありますが、
今回は【出産当日の分娩後】、つまり“誘発分娩のその後”について記録しておこうと思います。
アラフォー高齢出産・妊娠高血圧腎症・管理入院を経ての出産。
同じように不安な気持ちを抱えている方の参考になれば嬉しいです。
赤ちゃん、生きてる?
急な陣痛から、気づけば出産に至っていました。
子宮口全開→出産まで一気に進み、あっという間の出来事。
でも――赤ちゃんの泣き声が、聞こえませんでした。
息をしているようにも見えず、「大丈夫なの?」という不安が一気に押し寄せてきました。
「産まれたよー」と顔を一瞬見せられ、
「おめでとうございます」と言われたものの、抱っこはできず。
今までの子たちは、産まれた瞬間に泣いて、臍帯を切って、胸に抱いて…までが“出産の流れ”でした。
でも今回は違っていました。
入院中に何度かあった胎児の異常、陣痛中に酸素マスクをつけられた時の「心拍が下がっている」という声が頭をよぎります。
――この子、大丈夫なのかな。
処置台の向こうで吸引されたり保温されたりしている最中、ようやく小さな泣き声が聞こえました。
その瞬間、「よかった、生きてた」と心の底から思いました。
37週0日で誘発分娩となり、
自身で誕生日を選べたなかった我が子。
2000g未満のとても小さな赤ちゃん。
はじめての抱っこと夫との対面
諸々の計測が終わったあと、ようやく私の胸にやってきた赤ちゃん。
助産師さんが動画を撮ってくれたり、抱っこしている写真を残してくれたりしました。
すごく小さくて、細くて、どう扱えばいいのか分からないほど。
「壊れそうだな…」と感じながら、そっと腕に抱きました。
その後、夫が到着。
兄弟たちは入れなかったので、夫だけが分娩室に入り赤ちゃんと対面。
夫は、小さい赤ちゃんを見る機会が多くあったため、
3,000g前後の兄弟を見て「大きい」と言ってたくらいでした。
でも、第三子は、明らかに小さく産まれましたが…
「小さいね」とは言わず、ただ静かに抱っこしていました。(その瞬間、写真を撮り忘れたのが今でも悔しい😨)
小さなカンガルーケア
計測を終えた赤ちゃんは、再び私の胸の上へ。
ミャーミャーというか細い声で泣いていて、助産師さんが教えてくれました。
「赤ちゃんは目が見えないけど、匂いでおっぱいを探すんだよ」
「おっぱいの近くに抱っこしてたら、自然に吸いにくるよ」
小さすぎて私の乳首を吸うほどの力はなかったけれど、
一生懸命探そうとする姿がたまらなく愛おしかった。
自発呼吸も安定していて、「今日は一緒に過ごせそう」と言われ、
小さな生命の温もりを感じながら、夜を迎えることができました。
胎盤の娩出・出血🩸について
お腹が空いて「ごはん食べたい」と思った私ですが、
まだ胎盤の娩出が終わっていなかったため、
まずは「すべてを産みきる」ことに専念。(当たり前なんですけどね。)
赤ちゃんがバタバタした中、スポーンと出ていってしまった感があった分、
「胎盤って、こんなに静かに出てくるんだ…」と
素朴な感想を抱きました。
ありがたいことに、胎盤が出たあとも出血は少量。
私は毎回、母子手帳に“出血量:少量”と書かれるタイプで、
もはやカウントするほどでもないくらい。
産後出血が多く大変だった、病院に転送されたなんて話を聞く中で、
「私の子宮?筋肉?血液の凝固機能?ちょっと優秀かも」と思った瞬間です。
胎盤と臍帯血のこと
胎盤が出てきたあと、医師から
「一応、検査に回しますね」と言われました。
パッと見た感じでは、胎児発育不全の明らかな原因はなさそうとのこと。
そして、「臍帯血(さいたいけつ)」の保管について。
実は、これは出産前にあらかじめ調べて、手続きを済ませていたこと。
第一子・第二子のときは保管していなかった私ですが、
今回は少し違いました。
妊娠中、臍帯血が小児がんや再生医療、発達障害の治験などに使われていることを知り、
「この子の誕生の瞬間にしか取れないもの」だと強く意識するようになりました。
妊娠中に何度も悩みながら、最終的に“民間の臍帯血保管”を選んでいました。
公的施設か民間施設の違い
妊婦健診で受診する時、何度か病院に相談しました。
「公的な臍帯血バンクなら調整できますが、民間の場合はご自身で手配してください」とのこと。
主治医が固定ではないため、担当医によって温度差がありましたが、基本的な返答はみんな一緒。複数の医師がいて、その都度診察する医師が違うのは、さすが大学病院って感じでした。
臍帯血はあくまで研究段階のようで、
病院側から「強くおすすめされる」こともなく、
赤十字の資料を複数もらった程度。
採取できるかどうかも、量や感染症の検査結果次第で変わるそうです。
取れない人も一定数いるとか。
そして公的と民間の明確な違いは──
「お金」と「自分や家族のために使えるかどうか」。
民間バンクは“自由に使える”分、費用は自己負担。
「日割りで見たらそんなに高くない」という宣伝を見ても、
まとまった額を払うとお財布にはずしっと響きます。笑
私が臍帯血を保管すると決めた理由
それでも、私は民間の臍帯血保管を選びました。
理由は2つあります。
ひとつは、家族のがん罹患率が高いこと。
もうひとつは、子どもの発達への小さな不安があったことです。
診断には至っていませんが、少し自閉症傾向があり、
関わり方だけではどうにもならない部分も感じていました。
今後、研究が進んで臍帯血が、小児がんや自閉症などの治療や支援の糸口になるなら、
最後の妊娠・出産である今回。
「これが最後のチャンスかもしれない」──
そう思ったのです。
兄弟間でも臍帯血が使える可能性があると聞き、
未来への小さな希望を込めて、保管を決めました。
💬 まとめ:産後当日に感じたこと
出産の瞬間、赤ちゃんの泣き声が聞こえなかった不安。
そして、息をしてくれたと分かったときの安堵。
わが子のために――と決めた“臍帯血保管”。
※臍帯血保管については、妊娠中から調べ、実際に経験した知人の話を参考にしました。
次回以降の記事では、無事に保管できたのか。
実際に契約するまでの流れや費用面も含めて詳しく紹介したいと思います。
ジェットコースターのような数時間を過ごし、
全身の力が抜けたような、でも心は高ぶったまま。
疲れているはずなのに、
すぐそばにいる小さな命のぬくもりを感じて、
アドレナリンが止まらなくて――眠れませんでした。
次回は、赤ちゃんとの一晩とその後についてお話ししたいと思います。


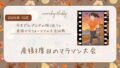

コメント